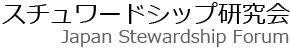投函者(三井千絵)
脱炭素の国際的な枠組みから離脱する日本の金融機関が話題になっている。日本より3ヶ月早く株主総会シーズンを迎える海外では、様々なバックラッシュの影響を受けたと思われる株主提案も見られるようになった。その一方、欧州委員会は先日、予定されていたサステナビリティ開示を緩和する法案を提出し、対象となっていた日本企業が今後の対応の見直しを検討すると報じられていた。
このような中、投資家の今後の行動については誰しもが気になるところだろう。そこで投資家や関連するプレイヤーが今どのように感じているか、緊急アンケートを実施した。本稿ではその結果について紹介していきたい。
アンケートは3月12日から23日まで実施をし、27名の回答が得られた。
回答を控えた投資家
回答者の半数弱である44.4%はアセットマネージャーで、次に多かったのは自分自身の年金運用を考えた個人としての回答(18.5%)、また11.1%は年金基金などアセットオーナーであった。回答者の40.7%は欧州、25.9%が日本、22.2%が日本を除くアジアであり、「その他」という答えが11%あったが、本来選択肢で足りるはずで、「その他」を選んだのは”回答を控えた”・・・と見るのが正しいかもしれない。実際「このアンケートには答えられない」という返信を複数、北米から受け取った。
アンケートでは「現在、投資やエンゲージメント、議決権行使において、ネガティブなプレッシャーを感じるか」について、Q1.気候変動、Q2.ESG、Q3.DEIに関しそれぞれ5段階から選んでもらった。またQ4として「将来をどのようにみているか」、Q5「投資家はどうするべきか」、そしてQ6「企業の経営者に、長期の企業価値のために求めるもの」について、合計6問答えてもらった。後半の3問は自由記載であり、回答は選択型より時間がかかったと思われるが、27名のうちこの欄をスキップしたのは1人だけ(部分的にスキップしたのは3名)いただけで、その他の全員が何らかの記載をしてくれたことからは、投資家側の関心の強さも感じられた。
最もネガティブなプレッシャーを感じるのはDEI
回答者全体で合計をすると、Q1の気候変動についてはそれほどネガティブなプレッシャーを感じないという回答が44.4%と最も高かった。次に「いくらか感じる」という回答も25.9%、「強く感じる」が3.7%であった。しかしこれがQ2のESGになると「いくらか感じる」が33.3%、「強く感じる」が7.4%に増え、「それほど感じない」は25.9%になった。そしてQ3のDEIに対しては「強く感じる」、「いくらか感じる」、「少し感じる」がすべて22.2%、「それほど感じない」は18.5%と減った。何の質問にも「感じない」という答えが18.5%あった。
回答者をEUと、日本を含むアジアに分けてみてみると、EUは気候変動についてはネガティブなプレッシャーを「それほど感じない」が45.5%、「感じない」が27.3%なのにたいし、DEIについては「強く感じる」、「いくらか感じる」がそれぞれ27.3%(つまり合計で過半数)となっている。これに対し日本及びアジアの投資家は、気候変動については「いくらか感じる」が35.7%(しかし「それほど感じない」も50%)と少しEUよりもネガティブなプレッシャーを感じる人が多い一方、DEIについては「少し感じる」「それほど感じない」がそれぞれ28.6%となっており、その傾向はやや弱い。それでもやはりDEIのほうが、どの地域でもESGよりもネガティブなプレッシャーを感じ、気候変動についてはこれらの二つに比べれば、それほど感じていないというのは共通しているようだ。
今後の方向性、投資家がすべきこと
記述回答についてQ4の「今後の方向性」については、EUの投資家からは、米国と世界の分断や政治家のプレッシャーなど将来を否定的にみている意見もあるが、過半数は「混乱は一時的」、「ESGがより実質的になる」と答えている。興味深いのは「EUではESGに対する反発がみられる」と自地域のこととして捉えている意見だ。
日本及びアジアの投資家からは、「日本企業はより良いESGに向かって変わらず行動している」という意見が複数みられた。また短期的には米国の影響があるかもしれないが、長期的にはかわらない、ESG、気候変動、DEIは株主にとって重要といった意見が大半であった。
Q5の「投資家がすべきこと」については、EUの投資家は、落ち着いて、長期的なリターンを求め、明確なメッセージを市場に発信するべき、といった意見が得られた。何か評価がかわったわけではない、社会や環境の問題に引き続き目を向けるべき、道徳的、倫理的姿勢を取るべきと、回答者は全員が基本的にはこれまでの取り組みを続けるべきという意見で、信念のようなものを感じさせた。これに対し日本及びアジアの投資家は若干異なっていて、リスク管理、データ分析にもとづいた投資決定が必要といった回答が腹痛みられた。またエンゲージメントについて言及した人が多く、「企業が問題を理解するようにエンゲージメントする」といった声があった。日本及びアジアではESGや気候変動の取り組みはまだ取り組みの過程で、効果が得られるよう模索している段階なのかもしれない。
長期の企業価値のために企業の経営者に求めること
最後の質問である、Q6「企業の経営者に求めること」については、EUの投資家は、重要な持続可能性のリスクと機会を開示し、対処し続けて欲しい、というなかで「DCFをガバナンスの中心に」、「規律ある投資/資本配分」、「短期のことにも目を向けて」というコメントがみられた。一方日本及びアジアの投資家からは「イノベーションの強化」、「長期的な価値創造」、「中期/長期のビジネスを継続的に再評価し再構築すること」、「開示・ガバナンス強化」、「株主利益を高めるという哲学」といった、やはりESGやDEIがどうというより、コーポレートガバナンス改革のもと、日頃から求められている点があげられた。
現時点では、日本の投資家においては企業に対する投資、エンゲージメント、議決権行使に対して、何か変わるということはないようだ。これはひと足先に脱炭素に関する国際的な枠組みから離脱した金融機関にとっては、なんらかの理が通る説明が必要だということだろう。もちろんこのようなアンケートに答えることができた投資家は限られるが、答えなかった投資家ももしそれが「意見が異なる」から、であればアンケートに答えないほどの理由とは思えない。したがって答えられなかった投資家が参加しても、結果はあまり変わらなかったのではないか、と感じている。
またEUに比べて、投資家が日本企業に対し「ESGの取り組みになんら揺らぎがない」と信頼しているかのように感じられた答えがみられたことは、数年前を思うと感慨深い。ぜひ長期の企業価値向上を目指し、投資家と企業共に力をあわせて、短期的な不確実性を乗り越えることができたらと思う。