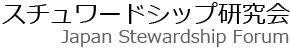投函者(三井千絵)
2024年4月に岸田元総理が、海外投資家団体に対して行った約束「有価証券報告書(以下、有報)の株主総会前開示に向けて、金融庁で検討をする」という発言から1年近くが経過した。2025年3月28日金融庁HPに、加藤金融担当大臣から改めて株主総会の前に有報を提出するよう「要請」が発表され、4月7日には金融庁が全上場企業を対象に有報を株主総会前に提出するか調査を行うことが報じられた。有報を株主総会の前に提出してほしいという投資家の声は実は古く、今度こそある程度の進展を期待している。
しかし、この欄でも過去執筆したように「有報」を今の株主総会の前に提出するには、株主総会のために準備する必要のある事業報告書との完全一元化が必要だろうし、サステナビリティ開示が追加されようとしている今、実際は難しいのではないかと思う。有報が株主総会の数日前に提出されるのでは意味がなく、事業報告書と置き換わるなら少なくとも3週間前に開示されていなければならない。十分な理解のないまま対応が進めば、それこそ「有報の簡素化」につながりかねない。そのような懸念があれば、「有報の株主総会前開示ではなく、株主総会を有報のあとに開催してほしい」と考える投資家がいても不思議ではない。
「投資家から有報を先にほしいと聞いたことがない」
ところで企業は「金融庁はそう言うが、株主総会の前に有報を提出してほしい投資家は本当にいるのだろうか」と思っているかもしれない。実際、日頃対話をしている投資家から、そう聞いたことがない企業が多いのではないだろうか。
これは少し複雑だ。もし投資先企業と良好な関係があり、大きな問題を感じていなければ、投資家自身も現在のプラクティスに慣れており「そんなに急ぐ必要はない」と答えるかもしれない。日本の投資家はパッシブ運用が多く、それぞれ投資先企業数も多い。そうなると一社一社の問題をそれほど深く(問題がない企業であれば)時間をかけてみることはできない。
なぜ有報が株主総会の前にあるべきという議論は、当然議決権行使のためだ。だから株主総会で厳しい投票が予想されるとき、これは投資家のためだけでなく企業にとっても重要となる。経営やガバナンスに問題があり、取締役選任をめぐって議論となれば、より詳しい情報が必要となる。何事がなくても、株主総会の翌日に巨額の報酬が支払われ「それであれば反対したのに」と株主が後悔に憤ることもある。しかしそのようなことがなければ、日本の投資家は長年のプラクティスにおいて「年間を通じてエンゲージメントしているから特に変える必要はない」と考えるのが一般的だろう。そうなると、不満を感じるのは本国のプラクティスと異なっている海外投資家となる。
海外の投資家からみた日本の不思議
今は「有報の総会前開示」が”キャッチフレーズ”になってしまったが、決して有報を前に出すことだけが海外投資家から求められたことではないと筆者は考える。そして日本には、海外と比べて非常に異なっていて、海外の投資家がこれまで意識すらしていなかった問題がある。それは基準日が株主総会より3か月も離れていて、それが定款に書かれているということだ。
有報を株主総会の前に見たいということは、決して有報を今より早く出してほしいという意味ではない。しかし株主総会の開催日の変更がそれほど難しいということは、特に海外の投資家にはほとんど知られていない。法律で基準日から3ヶ月以内に実施しなければならないとされており、現在の総会はそのギリギリに行われていること、基準日は定款に書かれており変更には株主総会が必要・・・というのは他国と大きく異なっている。基準日は英国やフランスは総会開催日の2日前、その他の国も10日とか、長くても数週間前が基準日となっている。日本では仮に有報だけを株主総会の前に出しても、それい納得して新たに株式を取得して議決権を増やすことはできず、逆にそこで売却しても株主総会での議決権は残る。有報、総会のスケジュールになっても、その効果は他国と完全には同じにならない。
株主提案
2023年3月末、業績が急回復する中で女性取締役候補者ゼロであったキヤノンでは御手洗会長兼CEOの賛成率が50%ギリギリとなった。今年4年連続赤字となったKLabでは森田社長は株主総会において過半数の賛成票を取得することができなかった。取締役選任議案が否決される可能性はどの企業にもある。しかし株主提案が行われれば、その緊張感はさらに高まるだろう。たいていの株主提案は取締役選任議案に対し行われる。特定のビジネスをめぐり取締役を送り込むという形であったり、既存の取締役に対する反対となる。過去には、長期投資家はそれに応じることは少ないとみていた企業もあるだろう。このような提案に全力で対応することができるのは、投資先企業が少ないアクティブ運用を行っているケースだと考えられていたからだ。しかしキャノンのケースをみてわかるように、ここ数年日本のコーポレートガバナンスは特定のテーマに対し投資家の行動を明確化している。そして企業価値向上を取締役が果たせるのかどうか、資本効率を高めることができるのかといったテーマがより注目されている。そのため企業も監査済み財務諸表を従え、より真剣な説明をする必要が高まっている。
だから筆者は、投資家ではなく企業自身のために株主総会を有報の後に開催するべきだと考える。その日まで真剣に経営をしてきているのであれば、有報がもっとも投資家に訴えることができる資料となるし、さらにその後基準日が設定されていれば、有報をみてからさらに買い増しをする機関投資家もあるかもしれない。
定款変更
基準日の変更には定款変更をする必要がある。定款変更は株主総会でしかできない。したがって今年の株主総会にそれをかければ、来年やっと株主総会の日程が変更できるということになる。6月総会の企業はGW明けに続々と総会議案が決定していることだろう。今年議案に入れていなければ、株主総会の開催を遅らせるのにはさらにまた一年待たなければならないことになる。果たして各社は何らかの検討をしているだろうか。
5月8日、トヨタは決算短信によって今年も有価証券報告書は株主総会の後の提出であること、また別途6月12日に開催される株主総会の第一号議案が定款変更であることを発表した。この定款変更は、今のところ分かっているのは監査等委員会設置会社への移行であって、株主総会基準日の変更が含まれるのかどうかはわからない。そうでなければ、株主総会の日程変更にはさらに1年待つことになる。
トヨタは過去2年つづけて株主提案をうけとっている。気候変動に対する対応で、昨年11月の米国大統領選挙の結果や欧州のオムニバス法案などもあり、今年提出されても賛成率は伸びないかもしれない。だからいますぐ株主総会を有報のあとに変更しようと感じないかもしれない。しかし上記のトヨタの決算説明会においても佐藤社長は、米国のEV車に関する規制がかわることについて何らかの戦略変更があるかと問われ「規制のためにやっているわけではない、気候変動対応はやらなければならないことだ」と堂々と発言した。今こそ日本企業のリーダーシップに世界は期待したいかもしれない。そのような中、株主総会を有報開示後、その企業の将来に期待する最新の株主とともに迎えるよう、企業もぜひ前向きな対応をしてもらいたいと思う。