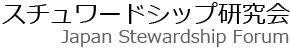投函者(三井千絵)
ADB(Asian Development Bank(アジア開発銀行))は、JAPAN WEEKS中の10月22日から24日、東京で第44回ABMI ASEAN+3 Bond Market Forumを開催した。ABMIとはAsian Bond Markets Initiativeの略で、2003年の第6回ASEAN+3財務大臣会議で合意された「アジアにおいて効率的で流動性の高い債券市場を育成し、アジアにおける貯蓄をアジアに対する投資へと活用できるようにする」ことを目的としたものだ。このイニシアチブのもと、2010年からASEAN+3域内のクロスボーダー債券取引を促進することを目的として、ASEAN+3 Bond Market Forumを開催するようになった。それから15年、年3回開催しているためこのフォーラムは既に44回もの開催を数えている。
2、3年前からこの会合はサステナブルファイナンス一色になった。ADBでも2020年に最初のサステナビリティボンドを発行している。ASEAN各国のサステナビリティの取り組みは、米国やEUが”バックラッシュ”と言われる中、その推進力に変化はほとんど見えない。本会合でもインドネシア、フィリピン、カンボジアの金融当局によるパネルがあり、各国当然のようにISSB開示の導入計画を披露した。マレーシアの金融当局を引退後Sustainable Finance Institute Asia(SFIA)のCEOを務めるユージン・ウォン氏は、過去にもこのABMIのカンファレンスでASEAN各国のタクソノミの比較などを発表してきたが、この第44回でも何度か登壇した。そのうちの一つはSMEのサステナビリティ開示についての取り組みだった。
ASEANにおけるSMEのための、開示の実証実験
SFIAは、東南アジアには多くの中小企業(SME)があり、グローバル企業のサプライチェーンに組み入れられているため、今後彼らがどのようにサステナビリティ開示ができるかどうかは、大きな課題だと考えていた。そしてSMEの開示を促し、支援する実証実験を計画した。 実証実験「Single Accesspoint for ESG Data (SAFE)」 は、SMEの開示に役立つ最小限のESGデータセットをGRIらと一緒に開発し、それをもとに企業がステークホルダーに有効に説明(開示)し、その成果を感じられるか実証をするプロジェクトだ。用意したデータポイントは40〜50で、サプライチェーンの先にいる上場企業がサステナビリティ開示に必要な情報を含んでいる。この実証実験には日本のSME向け開示スタンダード(SDSC)の運営事務局も務める日本のITベンチャーSustainable Lab(以下、サスラボ)も参画し、サスラボの稼働実績のあるプラットフォーム型ツールであるTERRASTの一部の機能を、この実験のプラットホームとして提供した。
SFIAのSAFEのプロジェクトには、フィリピンの経産省にあたるDTIが地元企業に、またASEAN business Advisory Countil もASEAN各国から参加を募った。タイのホテル産業やベトナムの半導体企業など様々な企業が50社ほど参加し、サスラボが提供したプラットホームにデータを入力し、実験終了後参加企業のフィードバックを得た。プラットホームには排出量計算ツールも接続し、入力データをもとに計算をし、サプライチェーンの排出量報告に用いることもできる。参加者からは、このようなデータ共有プラットホームは有益だという声が得られたそうだ。
サステナビリティデータをつなぐプラットフォーム
それではサスラボのTERRASTとは何か。これはデータの収集、管理、分析(スコアリング)など様々な機能を持っているが、SME向け事業については、現在地方銀行と連携し進めており、その投融資先の中小企業とのデータ共有に用いている。投融資先にツールを通してデータを入力してもらっているようだ。銀行がこういったツールを導入するインセンティブは投融資先のESGデータ、特に排出量などを同一フォーマットで収集するという点で、これは銀行からすれば、ファイナンスド・エミッションの計算などに役立つだろう。一方、入力する中小企業のインセンティブは、対銀行とのより良いエンゲージメントであろう。とはいえ、ESGのデータとなると中小企業の中には、何をどう入力したら良いかわからないケースもあるかもしれない。その支援は、このようなプラットホームの提供者が合わせて提供するのが良いのかもしれない。
サスラボは、このような地方銀行を中心とした地元のサプライチェーンのデータが収集できれば、日本全体の中小企業の状況を把握する強力なデータレポジトリになれるのではないかと期待している。これは先のSAFEの例でも同様だが、それぞれの銀行が自らの投融資基準を持ち、それに合わせてデータを求めるだけであれば、個別にシステムを利用するだけとなる。しかし自らがISSB基準などで報告義務がある銀行であれば、自ずと標準的なものを必要とするだろう。その結果それぞれが投融資先に求めるデータも、標準化できるかもしれない。
TERRASTにはデータ提供機能もあり、その部分を利用している機関投資家のA氏は、「上場企業の非財務情報の収集やその開示サポートに比べ、SMEの分野はフロンティア事業としてのチャレンジと思う。しかしSMEのデータプラットホームが構築できれば、サプライチェーン管理を行う大手企業・地域金融機関だけでなく、未上場投融資においても利便性が高まるだろう。また日本企業が事業進出している東南アジアへの拡大は、今後必要な分野への取り組みとして注目したい」と述べている。
サプライチェーンを支えるSMEと、サステナビリティデータ
今日本では、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示は、時価総額1兆円以上の企業以降のスケジュールはまだはっきりしない。プライム、あるいは全ての上場企業がいつかは対象となるのかどうかも不明だ。決められない理由はなんだろう。時価総額の小さい企業には難しい、ということだろうか。時価総額の大小とサステナビリティ情報の必要性には何か関係はあるのだろうか。
ただ、サステナビリティはサプライチェーン全体の問題だ。規制の進展を待たずとも、もしかしたら利便性によって、足元で小さな企業の情報開示も意外と進んでいくのかもしれない。