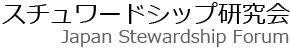投函者(三井千絵)
有報サステナビリティ開示とEDINETタクソノミ
グローバルのサステナビリティ開示基準の開発、その(有報のような)制度開示への適用、保証の導入が世界中でもう5年近く議論されてきている。日本でも今なお進行形ではあるが、2027年から上位70社ほどの企業が有報においてサステナビリティ開示を行う流れの中、8月8日から9月8日まで金融庁では電子開示システムEDINETの対応についてパブコメが実施されていた。
2008年から金融庁のEDINETは、有報などを提出するときXBRLと言うフォーマットで提出することを義務付けている。これはブラウザで表示するための、文字の位置などを指定するタグに加えて、”売上高”など財務諸表の情報をデータとして抜き出せるよう、それぞれの情報の意味を表すタグが挿入されている。提出書類の開示要件にあわせて、挿入するタグのリスト(EDINETタクソノミ)を金融庁が用意している。書類全てにタグ付けをするため、タクソノミは事実上開示要件の一覧になる。毎年開示府令や開示基準の改正が行われると、EDINETタクソノミもあわせて改訂される。海外の多くの国でも、金融当局や取引所が開示書類の提出を求める際にXBRLを用いている。
この様なフォーマットで提出させる目的は、提出された書類に間違いがないか自動的に検査したり、利用者にデータを利用しやすくすることだ。アジアの金融当局では提出時あるいは提出後すぐに当局がチェックすることを目的に適用している場合が多い。一方東アジアや中近東の取引所などで導入時、海外の投資家のデータ利用を促進し、より投資をしてもらいたいという目的を掲げていたケースも耳にした。
2013年、日本ではこのタグづけを非財務情報へ拡大させた最初の国になった。海外の当局は関心を示したが、有報ほど非財務情報が定型化していた国は他になく、同じ様な適用はできなかった。その後GRIやSASBなどグローバルにサステナビリティ開示基準を作成する団体は独自のタグ(タクソノミ)の開発をはじめた。それまでタクソノミは提出システムに合わせてデザインされていたため、表形式で開示されていればその表通りにタグをふることが多かった(大株主の一覧や役員の一覧など。表の何番目に記載されたということを示すタグが用意されている)、特定の提出システムのためではないGRIやSASBのタクソノミは、情報の単位(排出量とか女性取締役の人数、など)でタグを用意するようになった。そしてISSBも基準にあわせたISSBタクソノミを開発した。日本が日本版のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を開発する中で、サステナビリティ情報のタグをどうするかということでこのパブコメが行われたのだ。
非財務情報のデータ化への格闘
A氏は、EDINETから定期的に政策保有株の情報を取得し分析している。2013年からタグ付けが始まった情報だが、全ての企業の政策保有株を収録し分析するというのは、かつては情報ベンダーのデータベースに頼る必要があった。しかし今はEDINETが提供するAPIを用い、自作のソフトでEDINETから有報をダウンロードし、XBRLのタグでデータを取り出して自分で分析できる。A氏はタグ付けが行われたことで、政策保有株の日本企業全体の透明性は高まったと感じている。
ところがある日、ありえない数値を示す企業が現れた。統計的にみていて異常値が表れるため気がついたのだが、当該企業のPDF(EDINETでは、提出XBRLファイルからPDFを自動生成しており、有報を”見る”だけの利用者はこのPDFを利用する)を見ても、おかしいところは見つからない。時間をかけて調べXBRLで設定された株数の桁が間違えていることに辿り着いた。当該企業に連絡してもIR窓口に何が問題か伝わらず、説明して再提出してもらうのに大変な時間がかかった。A氏はそこで疑問を感じた。XBRLは誰の確認も経ず提出されているのだろうか。今回は極端な数字になったため気がつくことができたが、もしもっと小さい間違いだったら気づくことはできない。いったいどこまで正しいと信用して良かったのか、間違いに気が付かず株価に影響を及ぼしたらどうなるのだろうか・・・
画面を見て人にわかる形で間違いがあれば、提出企業も監査法人もみているし、金融庁もレビューを行うため気が付くことができるだろう。しかしPDFとXBRLが、ある意味異なる結果になるのであれば、それは誰がチェックをしているのか、A氏は親しい監査法人のB氏に質問をした。B氏は監査業界ではXBRLでの提出がはじまった2008年からXBRLのタグをチェックする保証サービスの検討があるが、それを採用している企業は聞いたことがないと答えた。実際そのようなサービスを受けている企業がないわけではない。特に提出書類のクオリティの要求が厳しかった米国SECにも20Fを提出する金融機関などでは、監査法人の専門家からタグのチェックを受けるケースがあった。詳細な財務情報の提出を求められる米国では、各勘定科目のタグの数も多く正しく選択されているかどうかは財務諸表の作成と同じように難しい。そこで米国ではそのチェックを監査法人が行うというサービスが生まれた。
実は有報全体のタグ付けを全ての提出企業に求めている一方、日本の非財務部分のタグは少し粗い。詳細にタグがついているのは、従業員数や育児休暇取得率、株式所有者別一覧といった表形式で開示が求められている部分が中心で、多くはブロックタグという、各セクションごとにつけるタグだ。「事業等のリスク」という章にタグがつけられ、その個所をシステム的に特定することはできるが、文章で開示されていることもあり、その中でどんなリスクがあるかはタグづけされていない。そこで監査法人のチェックまでは必要性が認識されにくい。しかしこの質問をうけてB氏は改めて「これから個社性の高いサステナビリティ情報にタグが拡大するのであれば、監査法人がこの部分をチェックするニーズはあるだろうか」と筆者に問い合わせてくれた。
XBRLの間違い、だれの責任?
冒頭のパブコメで回答した情報ベンダーのC氏は、A氏と同じ悩みを2008年から抱いてきた。企業によってはタグづけの間違いが多く、そのまま信用して取り込めば自社のデータベースの質の問題となり、顧客に迷惑をかける。せっかくシステム投資をしデータを自動収録しても、その後人手でチェックをしていれば、そのメリットを十分に活かせない。誤ったデータが市場に出ても訂正までの間に動いた株価は元に戻せない。見た目がはっきりと間違えていれば企業自身の責任だと考える顧客も、XBRLだけが間違えていた場合、情報ベンダーの問題だと考える傾向がある。間違いが多い企業を調べて傾向を分析し、当局に訴えてもあまり問題を共有できなかったとC氏は感じてきた。一方で長年情報ベンダーとして財務情報の質に責任を持ってきたC氏は最近IT企業などがXBRLだけを用い、財務の専門家を置かず自動的に分析するツールなどを個人投資家向けサイトに出していることに心配を覚える。筆者も同感だ。誰もチェックしていないタグにアプリが自動的に行った分析結果を個人投資家が見ているのだ。これからAIも自動的に介在するだろう。
投資家が特定の企業のレポートを読むだけでは必要ないかもしれないが、情報ベンダーが開示された情報を正確に、利用できる形にしてデータベースに格納しようとするのはそれを活用する人がいるからだ。しかしその開示を決める場では、経営者の考えとか、マテリアリティの考え方といった文章で書かれる部分の議論は非常に盛んだが、それらがデータとして取得しやすい形式で開示されているかどうかについては、活発になりにくい。実際は文章中に記された「当社にとって何がマテリアリティか」について客観的に評価しようとすれば、同じ業種や同レベルの売上高・時価総額の多くの企業と比較することが本来必要だ。そのために情報ベンダーは、仮に4000社近い企業の8割近くが機関投資家に投資をされていなかったとしても、その全てを収録する責任があると感じている。そして人がよく見ていない企業の情報こそ、正確性が重要となる。それを手作業で行うには、コストが見合わないだけでなく収録できるスピードも情報量も限界があった。筆者が以前担当していた財務情報サービスでも、XBRLが導入されるまで1ヶ月かかっていた有報の情報収録は、(タグに間違えがなければ)秒の世界で収録が完了するようになった。そして以前より直ちに市場に影響するようになった。つまり基準の正確性や保証の議論と同じ様に、正しくデータとして収集されるためには、XBRLのタグがどのように提供されているか、またそのタグは正しく付与されているかという点も、市場全体にとっては前者と同じぐらい重要だ。表など開示に合わせたタグは、経験上タグづけ間違いは起こりにくい。しかし表を知っていればデータとして収録できるが、AIなどが自律的に判断して特定の情報を探す場合、あまり正確に情報を伝えることはできないかもしれない。”クオリティ”のあり方にも様々な切り口を考慮する必要が高まっている。
サステナビリティ開示タクソノミの議論に思う
サステナビリティ開示について、保証をどの様に適用するかの議論も決着していないなか、タグ付けの議論が始まっていることは良いことだと思う。しかし、どのようなタグにするべきかを考えるステージにたっているのだろうか。
タグのデザインには基準だけでなく、どのように開示が行われ、どのように収集されるかの観点が不可欠だ。たとえば先の政策保有株の間違いは誰かがチェックすれば解決するだろう。しかし日本市場で今最も注目されている課題を考えた時、今のような表示の順番を示すタグではなく、たとえば保有された株式が特定できるタグであれば、保有している側と保有されている側を機械的に照合させることもできるだろう。(現在は銘柄名のタグで切り出した日本語で名寄せをする必要がある)しかし一方でタグ付けを高度にすると、タグの選択が複雑になり企業名と一致しないといったミスを誘発するかもしれない。
このようなデータ利用者と合理的なレベルのタグ付けは、AIのレポート利用が盛んになるなか更に考慮しなければならない点が増えた。以前筆者がチャットGPTに筆者が所属する上場企業のスコープ3について問うたら、答えが引用している企業は全く別の企業だったことがある。現在EDINETタクソノミはスコープ3のタグを用意している。これがタグづけされればAIが参照先企業を間違えることはないかもしれない。しかし資産運用事業を行っており、ファイナンスドエミッションについて詳細な開示をしている場合、AIが正しく情報を抜き出すためにはどのようなタグづけがよいのかは、今まだイメージもつかないところだろう。そもそもその追加的開示を市場は求めるか(求める様な気がするが)その場合どのようにデータが取り出されるかは、過去の経験からも”開示がはじまってみないとわからない”のが現実と言えるのではないだろうか。
繰り返しだが、サステナビリティ開示のXBRLについてすでに議論が始まったことは良いことと思う。本当にデータが重要だと市場関係者に認識が広まっているのであれば素晴らしいことだ。だからこそ、その情報を収録する際果たしてどのようなデータがどのような形式で求められ、どのようなクオリティが必要となるかについては継続してよく議論するべきと思う。そしてそれにはどのようなタグであれば良いのか、それを正しく提出するには第三者のチェックが必要かといったことを広く実証しながら検討を深めていくことが望ましいのではないだろうか。