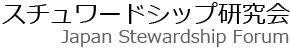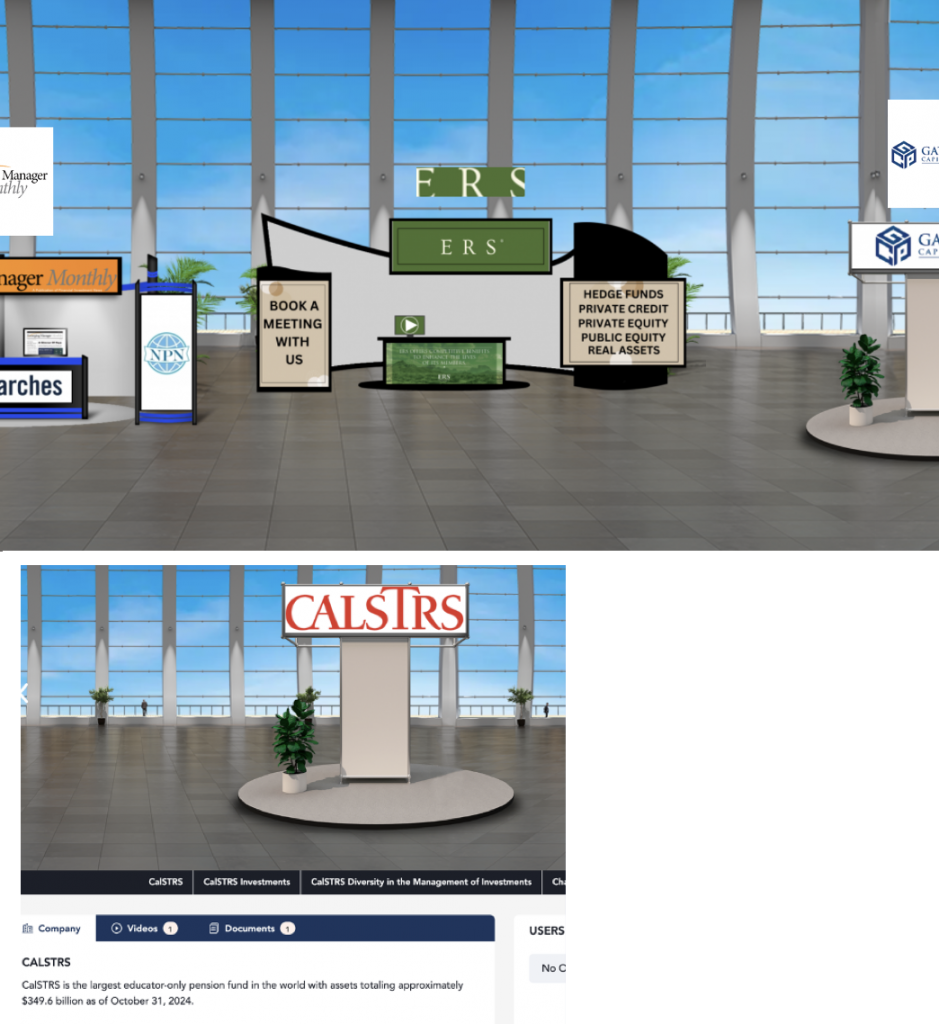投函者(三井千絵)
資産運用立国実現プランのもと、アセットオーナー・プリンシプルと日本版EMPが導入され、新興運用会社の活躍が期待されます。しかし新興運用会社が確実に成長するためには、よりよい新興運用会社プログラム(EMP)が必要です。この連載では海外のEMPを少しづつ紹介していきたいと思います。
深夜のバーチャルカンファレンス
2025年が明けると、米国企業が次々とDEIの看板を下ろし始め、日本企業や投資家の間にも今後の動向に対する不安が漂う中、2月11日(現地時間)テキサス州では新興マネージャー(EM)のためのバーチャルカンファレンスが行われた。
テキサス州教職員退職年金制度 (TRS) とテキサス州従業員退職年金制度 (ERS) は、2月11日、20回目となるEMのためのカンファレンスを主催した。「多くの参加を可能とするため」としてバーチャルで実施、参加費は無料だ。TRSは2,400億ドル、240万人の加入者を抱える大型基金で、EMPに力を入れていることでも知られている。申し込みをするとURLが届き、前日にはリマインダーも届いた。時間になってアクセスをすると、バーチャルのカンファレンス空間が現れた。(図1、上)凝った作りで、会場の入り口をクリックすると、画面は移り、バーチャルに会場に”入る”ことになる。(図1、下)
会場に入ったら右の「Panel Discussions」をクリックすると、今度はパネル会場に”移動”し、ライブ或いは時間が過ぎていればアーカイブでパネルを見ることができる。今年は現地時間の8時から9時に2つのパネルが予定されていた。一つは「How managers are addressing fundraising, staffing, distributions and more」というタイトルで、EMが独立を試みるとき直面する運用以外のこと、ファンドの立ち上げ方や、スタッフをどうするかといったことについての議論だ。EMが独立するときの運用以外の悩みごとは世界中同じようだ。もうひとつのパネルは「Insights into how capital providers evaluate potential partnerships」で、資金の出し手はどのようにEMを評価するのかについて取り上げていた。いずれも重要な議論だ。
資金の出し手との出会い
そして現地時間10時になると、アロケーターホールでのイベントとなる。左の「Allocator Hall」をクリックすると、40ほどの団体が”ブース”を並べている。
出店者の業種は様々であり、TRSと同じ公的年金としてカリフォルニア州教職員退職年金基金(CalSTRS)や同州職員退職年金基金(CalPERS)、イリノイ州教員退職年金制度、また財団、企業年金、新興マネージャーを必要とする資産運用会社、新興マネージャーやEMPを専門としたメディアなど様々な団体が出店している。(図2、上)ブースをクリックすると、その団体の詳細ページになる。(図2、下)当該団体がもつEMPの資料、ビデオ、またリアルタイムにチャットを交わしたりできる。現地時間の12時から13時をランチタイムとして除き、10時から15時まで、ここでコミュニケーションをとることができる。
これは日本時間にして午前1時から6時であり、参加は簡単ではないが、うまく睡眠時間を調整すれば、まるで深夜にゲームの世界に入り込んだような楽しさもある。
ファンドを立ち上げて3年目となる日本橋バリューパートナーの高柳健太郎氏は、このカンファレンスに2年前に参加した。アロケーターの時間になると、イリノイ大学基金に面談を申し込んだ。ほかにもいくつかやり取りをしたかったが、検討しているうちにあっという間にスロットは埋まってしまったそうだ。
「ミーティング当日は、プレゼンの準備をしてのぞんだが、カンファレンスのシステムが上手く動かず、予定の時間が終わってしまった。その後、メールのやり取りができ、戦略資料や会社案内などを送ったが、また将来チャレンジしたい。」とその時の体験を語っている。
ダイバーシティを求める基金たち
不勉強ながら筆者は、このカンファレンスを見てテキサス州のイメージを改めた。このようなITを活用する街という印象がなかったのだ。石油産業とステーキが思い浮かぶが、最近シリコンバレーからテキサスに拠点を移すITベンダーのニュースが聞かれるように、ハイテク産業も強い。テキサスに住む知人から「カラオケに行く時は数百キロ運転する必要がある」と聞いたことがあるが、ニューヨークからもカリフォルニアからも遠い米国の中心というのは、バーチャルが力を発揮する土壌でもあるのかもしれない。
もう一つ驚かされたのは、どのブースにいってもEMPを導入する説明に躊躇なく「DEI」が掲げられていることだ。運用というものは、そもそも多様化が基本だ。このバーチャルな空間では、連邦政府が何をいっているかなど、どこ吹く風なのだろうか。バーチャルの世界では相手がどのような民族で、どの国の出身であっても、関係がない。誰もがアクセス可能というような、ある意味イメージしてきた“アメリカ”の開放的な空気を感じた。
カンファレンスのあとも30日間はオンデマンドのメディア(パネルやブースの資料)はアクセスできるそうだ。テキサスまで出張する費用を負担しなくても、多くの団体と触れ合うことができる。日本の独立・新興マネージャーも、ぜひこのようなイベントを覗いてみてはいかがだろうか。新たな可能性のはじまりとなるかもしれない。